
小中大
2017年 3月 22日10:56 提供:東方ネット 編集者:兪静斐
作者:銭 暁波
前回の続きである。
世に名を馳せている「一品香」は、上海の地元の文人墨客のほか、その時代、多く上海に訪れた日本の文学者の回想録にもよく登場しているが、場合によって辛口評価も避けられなかったようである。
1921年、大阪毎日新聞社の海外視察員として上海に赴いた芥川龍之介は『上海遊記』の中で、次のように記した。「一体上海の料理屋は、あまり居心地の好いものじゃない。部屋毎の境は小有天でも無風流を極めた板壁である。その上卓子(テーブル)に並ぶ器物は、綺麗事が看板の一品香でも、日本の洋食屋と選ぶ所はない」、と芥川らしい、お決まりの貶しぶりである。
名声を轟かせるにつれ、「一品香蕃菜館」は、のちに「一品香大旅社」と改名され、ホテル経営になった。場所も今の西蔵路に引っ越され、今日の「来福士広場」の位置にあった。その立地の良さからみても当時の繁盛ぶりは想像に難くないであろう。そこに宿泊した日本文学関係者も少なくなかった。
村松梢風というと、今は思い出せる人は少ないかもしれない。若者の間では再び脚光を浴びている上海の別称「魔都」の名付け親である村松は1923年はじめて上海に渡り、その混沌とした雰囲気に魅せられ、『魔都』を発表した。のちにまた上海に訪れ、「一品香」ホテルに宿泊し、そこに足跡を残した日本の文学者の一人である。
吉行淳之介の父親の吉行エイスケも忘れ去られた文学者のひとりである。かつて新興芸術派として活躍していた頃、数度上海に渡ったことがあった。当時の上海を語る作品『新しき上海のプライヴェート』のなかには「一品香」ホテルをときどき夜の温柔郷の舞台として登場させ、文章自体は難解ではあったものの、エイスケならではの装飾の多い表現で夜の上海の艶めかしさをリアルに物語った。
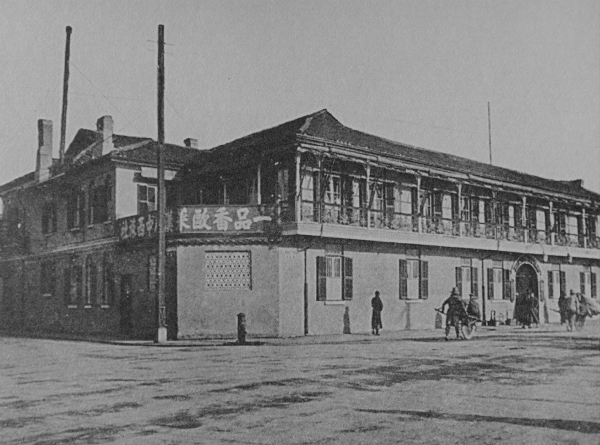
「一品香」は小説家にとって、ときに重要な舞台ともなった。このコラムにも書いたことがあったが、芥川と「因縁の深い」谷崎潤一郎は1926年、二回目に上海に訪れた際、宿泊先の「一品香」ホテルの部屋で当時親しく付き合った郭沫若と田漢と夜の十二時まで鼎談を行い、上海ないし中国のその時代の悲惨なる実情をあらためて知ったのである。(『上海交遊記』)。そのことは谷崎の創作にも大きく響いたようで、それ以来、谷崎はお伽話のような、いわゆる「中国趣味」の作品をぱったりと書かなくなった。
上海には租界という形が存在したからこそ古き伝統と西洋の新しきモダンが織り交ざった独特な文化スタイルになった。昔の上海の洋食もそうであったように、純粋な西洋料理というより、上海っ子の口に合うようにさまざまな工夫を凝らし、改良されたものが多い。いわば「海派」西洋料理の類である。
「音も立てず時代の歯車は二度三度と廻り…」、名優の森繁久彌がいうように、時代は過ぎ去る一方である。かつての上海の独特の雰囲気も味もだんだん薄くなりつつある今日では、「海派」はむしろ追い求め難い粋な文化のスタイルのひとつとなった。(了)
